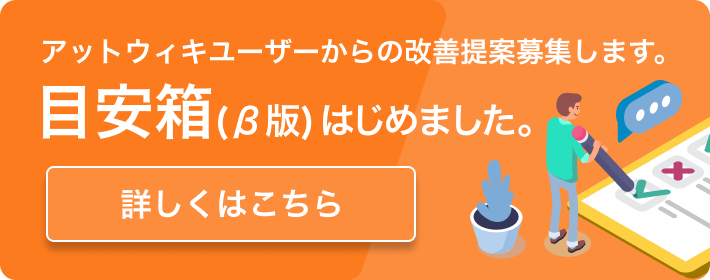激突! 王者VS王者!
天に煌くは数多の星々。無限の星雲の中心には月。
漆黒の宵闇にちりばめられた、金銀に輝く綺羅星達。
ぼんやりとした薄命が、朽ちたコンクリートを照らし出す。
「……っくくくく……」
ひび割れた灰色の壁の中、微かな笑い声が響き渡った。
「くははははははは……」
凋落の王城の中、1人笑う者がいる。
窓より漏れる天上の薄明。それをその身に受けながら、愉悦に口元を歪ませる者。
朽ち果てた古城に佇むのは、黄金に煌く女帝だった。
腰まで伸びる長髪も、前髪を押さえるカチューシャも、その身を包む堅牢な鎧も、全てが例外なく黄金色。
この世の黄金律の全てを支配したかのような、眩い光輝を放つ全身。
唯一その両の目だけが、鮮血の真紅に染め上げられていた。
「くく……なんとも滑稽なことだ。我(オレ)をこのような余興の出汁に使うとは」
その身に纏うのは王者の風格。
何物にもへつらうことはなく、何物にも屈することもない。
富、名声、武力。己の持ちうる力こそ、古今無双と信じて疑わぬ、絶対的なまでの自信。
そしてそのオーラの源泉は、それだけにはとどまらない。
豪奢な鎧も飾りではない。自信もただの妄信ではない。
全ての源は“力”の一文字。それらを持つに相応しき、圧倒的な強者の風格。
彼女の名はギルガメッシュ。
遥か古のメソポタミアの地、シュメール王朝時代のウルク第1王朝を統べる、人類最古にして最強の英雄王である。
「まったく、この世は未だに我を楽しませてくれる」
彼女自身、こうした殺し合いに巻き込まれたのは一度ではない。
そして本当の一度目こそが、既に死者であるはずの彼女が、現世に再び舞い降りた理由。
日本の冬木市を舞台に繰り広げられた、七大英雄のバトルロイヤル――聖杯戦争。
それを二度も経験したギルガメッシュは、今更このような事態に驚くこともない。
ただ、王として。
揺らぐことなき絶対者として。
その気高き魂と共に、悠然と構えるだけのこと。
「だがよいのか? 雑種よ」
首元の冷たさをなぞり、囁く。
傲岸不遜な哄笑と共に。
「貴様らの望みとは余興……雑種共の殺し合う様を、高みから見物することであろう」
両目の赤が仰ぐのは天。
その先に立つ、あのふざけた男女を見据えて。
「我様のような者を送り込んでいては、瞬きもせぬままに終わってしまうぞ?」
その通り。
彼はこの場にいるには強すぎる。
いかなる強者達が集おうと、所詮この戦場に集められたのは、有象無象の雑種に過ぎない。
ゲームとはあらゆる駒が拮抗してこそ、初めて観戦する価値があるというもの。
だが、この殺し合いは一体どうだ。ギルガメッシュという反則的なカードがいては、それこそワンサイドゲームで終了ではないか。
そんなもの、一体誰に楽しめよう。少なくとも彼自身は楽しめない。
人は圧倒的な強者に対し、チャンピオンの称号を与え、英雄として褒め称えるという。
しかし、それは自分がそいつよりも弱い場合の話だ。賞賛はコンプレックスの裏返しだ。
そんなもの、所詮最強の英雄王には理解できない。
それは連中も同じだろう。自分達こそが支配者であると妄信、あの傲慢な連中にとってもまた。
「そんなつまらぬ見世物を見ていて、楽しめるような人間か?」
全く愚かしいものだ。この程度の矛盾にも気付かぬとは。
王は大いに嘲笑する。
そして。
「いいだろう」
虚空より、抜刀。
聖杯戦争を戦う駒・サーヴァントの持ちうる宝具――《王の財宝(ゲート・オブ・バビロン)》の片鱗。
神話に讃えられた剣の原典が、英雄王の右手に握られた。
「望み通り、我がこの祭りをぶち壊してやろう。この場の雑種全てを駆逐し、ゲームを台無しにしてやろうではないか」
彼女とて現状を許したわけではない。
所詮雑種の分際で、自分の身柄を拘束し、このような殺し合いを命じた無礼者共を、決して許すわけにはいかない。
断罪が必要だ。
反逆者には罰を与えなければ。
ならばこれこそが、王の考えうる最高の罰則。
全ての参加者達を一方的に虐殺し、この殺し合いを陳腐なワンサイドゲームへと変えてやる。
そしてその果てには、彼らの後を追わせてやる。
ギルガメッシュの真紅の瞳が、危険な光を放っていた。
漆黒の宵闇にちりばめられた、金銀に輝く綺羅星達。
ぼんやりとした薄命が、朽ちたコンクリートを照らし出す。
「……っくくくく……」
ひび割れた灰色の壁の中、微かな笑い声が響き渡った。
「くははははははは……」
凋落の王城の中、1人笑う者がいる。
窓より漏れる天上の薄明。それをその身に受けながら、愉悦に口元を歪ませる者。
朽ち果てた古城に佇むのは、黄金に煌く女帝だった。
腰まで伸びる長髪も、前髪を押さえるカチューシャも、その身を包む堅牢な鎧も、全てが例外なく黄金色。
この世の黄金律の全てを支配したかのような、眩い光輝を放つ全身。
唯一その両の目だけが、鮮血の真紅に染め上げられていた。
「くく……なんとも滑稽なことだ。我(オレ)をこのような余興の出汁に使うとは」
その身に纏うのは王者の風格。
何物にもへつらうことはなく、何物にも屈することもない。
富、名声、武力。己の持ちうる力こそ、古今無双と信じて疑わぬ、絶対的なまでの自信。
そしてそのオーラの源泉は、それだけにはとどまらない。
豪奢な鎧も飾りではない。自信もただの妄信ではない。
全ての源は“力”の一文字。それらを持つに相応しき、圧倒的な強者の風格。
彼女の名はギルガメッシュ。
遥か古のメソポタミアの地、シュメール王朝時代のウルク第1王朝を統べる、人類最古にして最強の英雄王である。
「まったく、この世は未だに我を楽しませてくれる」
彼女自身、こうした殺し合いに巻き込まれたのは一度ではない。
そして本当の一度目こそが、既に死者であるはずの彼女が、現世に再び舞い降りた理由。
日本の冬木市を舞台に繰り広げられた、七大英雄のバトルロイヤル――聖杯戦争。
それを二度も経験したギルガメッシュは、今更このような事態に驚くこともない。
ただ、王として。
揺らぐことなき絶対者として。
その気高き魂と共に、悠然と構えるだけのこと。
「だがよいのか? 雑種よ」
首元の冷たさをなぞり、囁く。
傲岸不遜な哄笑と共に。
「貴様らの望みとは余興……雑種共の殺し合う様を、高みから見物することであろう」
両目の赤が仰ぐのは天。
その先に立つ、あのふざけた男女を見据えて。
「我様のような者を送り込んでいては、瞬きもせぬままに終わってしまうぞ?」
その通り。
彼はこの場にいるには強すぎる。
いかなる強者達が集おうと、所詮この戦場に集められたのは、有象無象の雑種に過ぎない。
ゲームとはあらゆる駒が拮抗してこそ、初めて観戦する価値があるというもの。
だが、この殺し合いは一体どうだ。ギルガメッシュという反則的なカードがいては、それこそワンサイドゲームで終了ではないか。
そんなもの、一体誰に楽しめよう。少なくとも彼自身は楽しめない。
人は圧倒的な強者に対し、チャンピオンの称号を与え、英雄として褒め称えるという。
しかし、それは自分がそいつよりも弱い場合の話だ。賞賛はコンプレックスの裏返しだ。
そんなもの、所詮最強の英雄王には理解できない。
それは連中も同じだろう。自分達こそが支配者であると妄信、あの傲慢な連中にとってもまた。
「そんなつまらぬ見世物を見ていて、楽しめるような人間か?」
全く愚かしいものだ。この程度の矛盾にも気付かぬとは。
王は大いに嘲笑する。
そして。
「いいだろう」
虚空より、抜刀。
聖杯戦争を戦う駒・サーヴァントの持ちうる宝具――《王の財宝(ゲート・オブ・バビロン)》の片鱗。
神話に讃えられた剣の原典が、英雄王の右手に握られた。
「望み通り、我がこの祭りをぶち壊してやろう。この場の雑種全てを駆逐し、ゲームを台無しにしてやろうではないか」
彼女とて現状を許したわけではない。
所詮雑種の分際で、自分の身柄を拘束し、このような殺し合いを命じた無礼者共を、決して許すわけにはいかない。
断罪が必要だ。
反逆者には罰を与えなければ。
ならばこれこそが、王の考えうる最高の罰則。
全ての参加者達を一方的に虐殺し、この殺し合いを陳腐なワンサイドゲームへと変えてやる。
そしてその果てには、彼らの後を追わせてやる。
ギルガメッシュの真紅の瞳が、危険な光を放っていた。
――かつり。
「ん?」
と。
不意に耳を打つ、音。
かつり、かつり、と。
聞こえてくるのは靴音だろうか。
微かに、だが着実に音量を増している。何者かがこのホテルの中にいて、自分の元へと近づいてきている。
こんなにも早く、それも向こうから獲物がやって来るとは、なかなかどうして幸先がいい。
迫り来る来訪者の気配を感じ、ギルガメッシュは悠然と構える。
そして、遂に。
ぎぃ、と。
扉が開かれた。
現れたのは1人の男。
全身を漆黒の装束に包んだ、英雄王と同じ金髪の少年が、その戸口より姿を現す。
その瞳は緑と赤。新緑のごときエメラルドと、灼熱のごときルビーのオッドアイ。
「ほぅ」
思わず、感嘆の声が漏れた。
衣服の色合いこそ地味なものだが、なかなかどうして、いい面構えをした奴ではないか。
ギルガメッシュの目が来訪者を見定める。
女性的な美貌を孕んだ端整な顔立ちは、かの騎士王の姿を思わせる。
翡翠と紅玉の色に分かれた、左右非対称なその瞳も、一種神秘的な雰囲気を放っていた。
「――高町なのはを知っているか」
そこへ。
ぽつり、と。
静かだが、確かな覇気と共に。
少年の口を突く、声。
「うん……?」
「俺の母さんを知っているか」
怪訝そうなギルガメッシュのことなどお構いなしに、少年はなおも問いかけを続けた。
「……礼を知らぬ奴め。王の御前に立つ者ならば、名を名乗るのが礼儀であろう」
英雄王の眉根がひそめられる。
眉間に浮かぶ微かな皺。無礼者への不快感の表れ。
発せられるのは静かな覇気。最強の王者の一端に過ぎぬとはいえ、並の人間であらば、それだけですくみ上がるほどのプレッシャー。
「……ヴィヴィオ」
それでも。
この者は平然と在り続けた。
覇者の気配に当てられることなく、なおも言葉を紡いだのだ。
このヴィヴィオとか言う奴、そこそこにできる。
少々意外に思いつつも、内心でギルガメッシュが漏らした感想だ。
刹那。
名乗りを上げた少年は。
「聖王――ヴィヴィオだァッ!」
怒号と共に跳躍した。
と。
不意に耳を打つ、音。
かつり、かつり、と。
聞こえてくるのは靴音だろうか。
微かに、だが着実に音量を増している。何者かがこのホテルの中にいて、自分の元へと近づいてきている。
こんなにも早く、それも向こうから獲物がやって来るとは、なかなかどうして幸先がいい。
迫り来る来訪者の気配を感じ、ギルガメッシュは悠然と構える。
そして、遂に。
ぎぃ、と。
扉が開かれた。
現れたのは1人の男。
全身を漆黒の装束に包んだ、英雄王と同じ金髪の少年が、その戸口より姿を現す。
その瞳は緑と赤。新緑のごときエメラルドと、灼熱のごときルビーのオッドアイ。
「ほぅ」
思わず、感嘆の声が漏れた。
衣服の色合いこそ地味なものだが、なかなかどうして、いい面構えをした奴ではないか。
ギルガメッシュの目が来訪者を見定める。
女性的な美貌を孕んだ端整な顔立ちは、かの騎士王の姿を思わせる。
翡翠と紅玉の色に分かれた、左右非対称なその瞳も、一種神秘的な雰囲気を放っていた。
「――高町なのはを知っているか」
そこへ。
ぽつり、と。
静かだが、確かな覇気と共に。
少年の口を突く、声。
「うん……?」
「俺の母さんを知っているか」
怪訝そうなギルガメッシュのことなどお構いなしに、少年はなおも問いかけを続けた。
「……礼を知らぬ奴め。王の御前に立つ者ならば、名を名乗るのが礼儀であろう」
英雄王の眉根がひそめられる。
眉間に浮かぶ微かな皺。無礼者への不快感の表れ。
発せられるのは静かな覇気。最強の王者の一端に過ぎぬとはいえ、並の人間であらば、それだけですくみ上がるほどのプレッシャー。
「……ヴィヴィオ」
それでも。
この者は平然と在り続けた。
覇者の気配に当てられることなく、なおも言葉を紡いだのだ。
このヴィヴィオとか言う奴、そこそこにできる。
少々意外に思いつつも、内心でギルガメッシュが漏らした感想だ。
刹那。
名乗りを上げた少年は。
「聖王――ヴィヴィオだァッ!」
怒号と共に跳躍した。
だん、と。
朽ちかけた床を強く蹴り。
ぱきり、と。
ひび割れたタイルを打ち砕き。
漆黒の闘衣をはためかせ、黄金の短髪を輝かせ。
「オオオオオオオオオッ!」
翡翠と紅玉の少年が、雄たけびと共に英雄王へと肉薄する。
瞬きの瞬間。開けた距離はゼロ距離へ。
振りかぶられるは右の拳。得物も何も持たぬ素手の一撃。反射的に剣で応じる。
激突。
きん、と。
ギルガメッシュの耳を打ったのは、しかし金属音だった。
真紅の両目に映されたのは、しかし細かな火花だった。
「ハッ! どこの馬の骨かは知らぬが、貴様も王を名乗る者だったとはな!」
肉の断たれる音はなく。舞い散る鮮血のしぶきはなく。
切り裂かれたはずのヴィヴィオの拳は、真っ向から切っ先とぶつかり合っていた。
ぎりぎり、ぎりぎりと。
刃を押していくのは重圧。華奢な少年の体躯からは、想像もつかぬほどの剛力。
なるほど、貴様もそうなのか。
英雄王は理解する。
この聖王を名乗る小僧もまた、かのサーヴァント達と同じく、人の理を外れた魔物なのだと。
ただ弱者を蹴散らすだけのゲームと思っていたが、これは存外楽しめそうだ。
「いいだろう!」
叫びと共に、一閃。
己が持つ強靭な筋力の下、刃金を勢いよく薙ぎ払い、ヴィヴィオの拳を振り払う。
瞬間、跳躍。
ただし聖王と同じではない。英雄王のそれはバックステップ。
決して距離を詰めることなく、優雅な動作で宙を舞い、すとんと背後に腰を落とす。
ギルガメッシュがその身を預けたのは、くすんだ赤いソファーの上。
長く放逐された年月の果て、埃を被り生地も劣化し、かつての色合いを失った玉座。
「この英雄王ギルガメッシュが直々に相手をしてやる。来るがいい、聖王」
余裕の表情を満面に浮かべ、手にした剣をヴィヴィオへと向けた。
一方、挑戦者の表情に浮かぶのは、憤怒。
当然だ。
明らかになめられているのだから。
椅子に座ったまま戦うなどとは、ふざけているとしか思えない。
「俺をなめてるのか」
「何を言う。慢心せずしてなにが王か」
哄笑。
返ってきた態度は不遜の一言。
お前とて王を名乗る者なら、それくらいは分かりきったことだろう、と。
それがヴィヴィオの神経を逆撫でたのか。整った顔立ちが険しさを増した。
その身に纏うは怒りのオーラ。見る者を圧倒する灼熱の憤怒。
「そうだな……ではこうしよう。我をここから落とすことができたなら、お前の母のことを教えてやる」
されど英雄王はその熱風を、微風のごとく受け止める。聖王がそうしたのと同じように。
雑種を黙らせることこそできても、相手は同じ王者なのだ。
王と王の闘争に、そんなものは意味をなさない。
そう。戦いを制すものは力。
戯れの言葉などではなく、力の現物を見せ付けて、敵を完膚なきまでに叩きのめすこと。
「さぁ」
刹那、空が割れた。
薄明と暗黒が支配する虚空に、無数の穴が穿たれた。
裂空の狭間より顕現するのは、天上の月明のごとき無限の輝き。
剣が。槍が。斧が。
矢がナイフが投げ槍が大鎌がレイピアがカタールが大槌がショテルがその他見たこともない異形の武具さえもが。
幾百幾千幾万の殺意が、鋭く苛烈な武具と化し、次元の彼方より狙いを定める。
これが。これこそが。
始祖にして究極の英霊が、生涯に渡り収集し続けた力。
唯我独尊、聖天八極。まさにそれを体現するに相応しき《王の財宝》。
「死ぬ気で挑め――聖王!」
朽ちかけた床を強く蹴り。
ぱきり、と。
ひび割れたタイルを打ち砕き。
漆黒の闘衣をはためかせ、黄金の短髪を輝かせ。
「オオオオオオオオオッ!」
翡翠と紅玉の少年が、雄たけびと共に英雄王へと肉薄する。
瞬きの瞬間。開けた距離はゼロ距離へ。
振りかぶられるは右の拳。得物も何も持たぬ素手の一撃。反射的に剣で応じる。
激突。
きん、と。
ギルガメッシュの耳を打ったのは、しかし金属音だった。
真紅の両目に映されたのは、しかし細かな火花だった。
「ハッ! どこの馬の骨かは知らぬが、貴様も王を名乗る者だったとはな!」
肉の断たれる音はなく。舞い散る鮮血のしぶきはなく。
切り裂かれたはずのヴィヴィオの拳は、真っ向から切っ先とぶつかり合っていた。
ぎりぎり、ぎりぎりと。
刃を押していくのは重圧。華奢な少年の体躯からは、想像もつかぬほどの剛力。
なるほど、貴様もそうなのか。
英雄王は理解する。
この聖王を名乗る小僧もまた、かのサーヴァント達と同じく、人の理を外れた魔物なのだと。
ただ弱者を蹴散らすだけのゲームと思っていたが、これは存外楽しめそうだ。
「いいだろう!」
叫びと共に、一閃。
己が持つ強靭な筋力の下、刃金を勢いよく薙ぎ払い、ヴィヴィオの拳を振り払う。
瞬間、跳躍。
ただし聖王と同じではない。英雄王のそれはバックステップ。
決して距離を詰めることなく、優雅な動作で宙を舞い、すとんと背後に腰を落とす。
ギルガメッシュがその身を預けたのは、くすんだ赤いソファーの上。
長く放逐された年月の果て、埃を被り生地も劣化し、かつての色合いを失った玉座。
「この英雄王ギルガメッシュが直々に相手をしてやる。来るがいい、聖王」
余裕の表情を満面に浮かべ、手にした剣をヴィヴィオへと向けた。
一方、挑戦者の表情に浮かぶのは、憤怒。
当然だ。
明らかになめられているのだから。
椅子に座ったまま戦うなどとは、ふざけているとしか思えない。
「俺をなめてるのか」
「何を言う。慢心せずしてなにが王か」
哄笑。
返ってきた態度は不遜の一言。
お前とて王を名乗る者なら、それくらいは分かりきったことだろう、と。
それがヴィヴィオの神経を逆撫でたのか。整った顔立ちが険しさを増した。
その身に纏うは怒りのオーラ。見る者を圧倒する灼熱の憤怒。
「そうだな……ではこうしよう。我をここから落とすことができたなら、お前の母のことを教えてやる」
されど英雄王はその熱風を、微風のごとく受け止める。聖王がそうしたのと同じように。
雑種を黙らせることこそできても、相手は同じ王者なのだ。
王と王の闘争に、そんなものは意味をなさない。
そう。戦いを制すものは力。
戯れの言葉などではなく、力の現物を見せ付けて、敵を完膚なきまでに叩きのめすこと。
「さぁ」
刹那、空が割れた。
薄明と暗黒が支配する虚空に、無数の穴が穿たれた。
裂空の狭間より顕現するのは、天上の月明のごとき無限の輝き。
剣が。槍が。斧が。
矢がナイフが投げ槍が大鎌がレイピアがカタールが大槌がショテルがその他見たこともない異形の武具さえもが。
幾百幾千幾万の殺意が、鋭く苛烈な武具と化し、次元の彼方より狙いを定める。
これが。これこそが。
始祖にして究極の英霊が、生涯に渡り収集し続けた力。
唯我独尊、聖天八極。まさにそれを体現するに相応しき《王の財宝》。
「死ぬ気で挑め――聖王!」
絶叫。
百獣の王のごとき咆哮。
それすなわち、心無き無限の軍勢への号令。
ぎゅん、と。
刃が空を引き裂いた。
数多の武具が一挙に加速し、眼下の聖王へと襲い掛かる。
その威力、神速にして猛烈。疾風迅雷とはこのことか。
一撃必殺の宝具の列が、今極大のスコールと化し、ヴィヴィオ目掛けて牙を剥いた。
「ぐぅ……っ!」
両手をクロスし、防御。
命中。命中。命中。命中。
かわす術などありはしない。視界の全てを埋め尽くす攻撃。
確かにその身は強靭なようだ。身に纏った衣服もただの服ではないらしい。
一振りの剣の一撃きりでは、傷一つつけられなかったのがその証拠。
しかし、それが十ならどうか。
二十ならどうだ。三十ならどうだ。人知を超えた神性の一撃が、何百何千と降り注ぐならどうだ。
今はまだ全て凌ぎきっている。それでも、苦悶の表情が消えない。唸りの声が止まらない。
「なめるなぁっ!」
雄たけびと共に。
遂に痺れを切らしたのか、ヴィヴィオは両腕を一挙に振った。
解かれる防御。しかし、同時に衝撃が解き放たれる。
刀が。パルチザンが。ハルバードが。虚しく虚空へ放り出された。
一瞬のブランク。されど、次の瞬間には更なる猛攻が迫る。
その気配を察知し、跳躍する聖王。
暴力の豪雨は対象を失い、その切っ先は背後の壁へと。
激音。波動。粉塵。爆砕。
粉々に破壊されるコンクリート。
四肢の全てを別の壁に張り付かせ、対岸の惨状を見届けるヴィヴィオ。
「まだだぞ」
だが、英雄王の攻め手は止まらない。
宝物庫の武具は尽きることを知らない。
すぐに更なる追撃が、聖王目掛けて殺到する。
「これはもう……覚えたっ!」
跳躍。
三たび飛び上がる漆黒と黄金。壁を蹴っての垂直跳び。
ぽう、と。
両手に宿されるは眩い光。
七つの色彩交じり合う、複雑にして神秘的な魔性の光輝。
煌きは球の形を成す。ボールとはすなわち投げるもの。両の腕が振りかぶられるのは必然。
「らぁッ!」
裂帛の気合。
解き放たれるのは人外の奇跡。
虹の光を纏いし弾丸が、迫り来る薙刀とモーニングスターを撃ち落とす。
怒れる聖王はなおも止まらず。
縦横無尽に虚空を駆け、神秘の光弾を投げ放つ。
さながら踊り子の舞踏のごとく。さながら猛獣の乱舞のごとく。
神聖であり、獰猛。
美しくもあり、荒々しくもあり。
今やヴィヴィオは敵の攻撃速度を完全に見切り、回避と迎撃を正確に繰り返していた。
「若い! 若いぞ聖王! まるで獣ではないか!」
されどギルガメッシュの余裕は消えず。
むしろ愉悦の笑みさえも浮かべ、眼前の舞曲を大いに堪能しているようにさえ。
「うる……さいっ!」
吼えながら、なおも光を放つヴィヴィオ。
百獣の王のごとき咆哮。
それすなわち、心無き無限の軍勢への号令。
ぎゅん、と。
刃が空を引き裂いた。
数多の武具が一挙に加速し、眼下の聖王へと襲い掛かる。
その威力、神速にして猛烈。疾風迅雷とはこのことか。
一撃必殺の宝具の列が、今極大のスコールと化し、ヴィヴィオ目掛けて牙を剥いた。
「ぐぅ……っ!」
両手をクロスし、防御。
命中。命中。命中。命中。
かわす術などありはしない。視界の全てを埋め尽くす攻撃。
確かにその身は強靭なようだ。身に纏った衣服もただの服ではないらしい。
一振りの剣の一撃きりでは、傷一つつけられなかったのがその証拠。
しかし、それが十ならどうか。
二十ならどうだ。三十ならどうだ。人知を超えた神性の一撃が、何百何千と降り注ぐならどうだ。
今はまだ全て凌ぎきっている。それでも、苦悶の表情が消えない。唸りの声が止まらない。
「なめるなぁっ!」
雄たけびと共に。
遂に痺れを切らしたのか、ヴィヴィオは両腕を一挙に振った。
解かれる防御。しかし、同時に衝撃が解き放たれる。
刀が。パルチザンが。ハルバードが。虚しく虚空へ放り出された。
一瞬のブランク。されど、次の瞬間には更なる猛攻が迫る。
その気配を察知し、跳躍する聖王。
暴力の豪雨は対象を失い、その切っ先は背後の壁へと。
激音。波動。粉塵。爆砕。
粉々に破壊されるコンクリート。
四肢の全てを別の壁に張り付かせ、対岸の惨状を見届けるヴィヴィオ。
「まだだぞ」
だが、英雄王の攻め手は止まらない。
宝物庫の武具は尽きることを知らない。
すぐに更なる追撃が、聖王目掛けて殺到する。
「これはもう……覚えたっ!」
跳躍。
三たび飛び上がる漆黒と黄金。壁を蹴っての垂直跳び。
ぽう、と。
両手に宿されるは眩い光。
七つの色彩交じり合う、複雑にして神秘的な魔性の光輝。
煌きは球の形を成す。ボールとはすなわち投げるもの。両の腕が振りかぶられるのは必然。
「らぁッ!」
裂帛の気合。
解き放たれるのは人外の奇跡。
虹の光を纏いし弾丸が、迫り来る薙刀とモーニングスターを撃ち落とす。
怒れる聖王はなおも止まらず。
縦横無尽に虚空を駆け、神秘の光弾を投げ放つ。
さながら踊り子の舞踏のごとく。さながら猛獣の乱舞のごとく。
神聖であり、獰猛。
美しくもあり、荒々しくもあり。
今やヴィヴィオは敵の攻撃速度を完全に見切り、回避と迎撃を正確に繰り返していた。
「若い! 若いぞ聖王! まるで獣ではないか!」
されどギルガメッシュの余裕は消えず。
むしろ愉悦の笑みさえも浮かべ、眼前の舞曲を大いに堪能しているようにさえ。
「うる……さいっ!」
吼えながら、なおも光を放つヴィヴィオ。
英雄王は笑顔の裏で、改めてこの見知らぬ王を分析する。
最初こそサーヴァント共と互角と評してはいたが、どうやら目の前の聖王とやらは、奴らともまた微妙に異なる存在のようだ。
そもそもサーヴァントというものには、7つのクラスが設けられている。
時に例外こそあれど、それぞれがそれぞれに特化した能力を持っているのが通常だ。
たとえば、ギルガメッシュ自身のクラスはアーチャー。
《王の財宝》より放たれる豪雨は、弓兵の絶対的な命中精度の下、百発百中の弾丸と化すわけである。
だが、この敵はまた事情が違った。
あの手から放つ光は、恐らく魔術の類だろう。それを得意とするのはキャスターだ。
しかしこのフットワークは、むしろライダーの持つそれである。
素手で宝具と互角にやり合った腕力はバーサーカー。敵戦力を分析する技量はセイバーのもの。
要するに、オールラウンダーなのだ。
そしてその性質上、サーヴァントにはこうした万能型は、絶対に存在するはずがないのだ。
(どうやらこのゲーム……思った以上に楽しめそうだな)
改めて、そう認識せざるを得なかった。
女帝の口元がつり上がる。表情が喜色に満たされていく。
サーヴァントと同等の実力を持ち、しかし全く異なる性質を有した未知なる敵。
そんな連中と刃を交え、叩きのめすことができると言うのだ。何と心が躍ることか。
「さぁ、どうした聖王! 逃げるだけでは王の名が泣くぞ!」
「言われなくても……!」
瞬間。
「っ」
その笑みが、固まる。
自信満々に叫んだギルガメッシュの、その慢心の笑顔が凍りつく。
鮮血の色を宿した瞳が、瞬時に大きく見開かれる。
その視線の先に映るヴィヴィオは――宝物庫の槍を、掴み取っていた。
「これでぇ――終わりだぁぁぁッ!」
刹那、絶叫。
咆哮と共に投擲。
自らの放った宝具の穂先が、今まさに敵の手によって、他ならぬ自分自身へと投げつけられる。
咄嗟に剣を振り、弾いた。
それだけでは終わらなかった。
ギルガメッシュが防御行動を取った、その一瞬の隙目掛けて。
「ウオオオオオォォォォォォーッ!!」
聖王ヴィヴィオの一撃が、英雄王を弾き飛ばしていた。
疾風怒濤。まさしく一陣の黒き風。
黒き装束をたなびかせ、豪雨を乗り越え一直線。
デイパックから取り出した、巨大な剣を振りかぶる。
野獣の咆哮に似た轟音と共に、のこぎりを彷彿とさせる刃が回転。
チェーンソー大剣の一振りが、ギルガメッシュの構えへと衝突。
完全に不意を突かれたのだ。
剣の重量。自身の加速度。刀身を覆う虹色の魔力。
いかに最強の英霊といえど、細身の剣の一振りで、三位一体の猛撃を受け止められるはずがない。
黄金の鎧は防御ごと弾かれ、ソファーから勢いよく投げ出される。
英雄王は玉座より落ち、無様に床を転げまわる。
「貴様……」
立ち上がるギルガメッシュ。灼熱の眼光が聖王を睨む。
こんな無礼者は初めてだ。
あろうことかこの男は、この英雄王の財宝を奪い取り、それを自分へ投げつけてきたのだ。
「言われた通り、落としたぞ」
怒りの矛先に立つ聖王は、無表情に自分を見下ろす。
許せない。
こんな屈辱が許せるものか。
こいつはこの場で八つ裂きにしてやる。この英雄王、直々にだ。
最初こそサーヴァント共と互角と評してはいたが、どうやら目の前の聖王とやらは、奴らともまた微妙に異なる存在のようだ。
そもそもサーヴァントというものには、7つのクラスが設けられている。
時に例外こそあれど、それぞれがそれぞれに特化した能力を持っているのが通常だ。
たとえば、ギルガメッシュ自身のクラスはアーチャー。
《王の財宝》より放たれる豪雨は、弓兵の絶対的な命中精度の下、百発百中の弾丸と化すわけである。
だが、この敵はまた事情が違った。
あの手から放つ光は、恐らく魔術の類だろう。それを得意とするのはキャスターだ。
しかしこのフットワークは、むしろライダーの持つそれである。
素手で宝具と互角にやり合った腕力はバーサーカー。敵戦力を分析する技量はセイバーのもの。
要するに、オールラウンダーなのだ。
そしてその性質上、サーヴァントにはこうした万能型は、絶対に存在するはずがないのだ。
(どうやらこのゲーム……思った以上に楽しめそうだな)
改めて、そう認識せざるを得なかった。
女帝の口元がつり上がる。表情が喜色に満たされていく。
サーヴァントと同等の実力を持ち、しかし全く異なる性質を有した未知なる敵。
そんな連中と刃を交え、叩きのめすことができると言うのだ。何と心が躍ることか。
「さぁ、どうした聖王! 逃げるだけでは王の名が泣くぞ!」
「言われなくても……!」
瞬間。
「っ」
その笑みが、固まる。
自信満々に叫んだギルガメッシュの、その慢心の笑顔が凍りつく。
鮮血の色を宿した瞳が、瞬時に大きく見開かれる。
その視線の先に映るヴィヴィオは――宝物庫の槍を、掴み取っていた。
「これでぇ――終わりだぁぁぁッ!」
刹那、絶叫。
咆哮と共に投擲。
自らの放った宝具の穂先が、今まさに敵の手によって、他ならぬ自分自身へと投げつけられる。
咄嗟に剣を振り、弾いた。
それだけでは終わらなかった。
ギルガメッシュが防御行動を取った、その一瞬の隙目掛けて。
「ウオオオオオォォォォォォーッ!!」
聖王ヴィヴィオの一撃が、英雄王を弾き飛ばしていた。
疾風怒濤。まさしく一陣の黒き風。
黒き装束をたなびかせ、豪雨を乗り越え一直線。
デイパックから取り出した、巨大な剣を振りかぶる。
野獣の咆哮に似た轟音と共に、のこぎりを彷彿とさせる刃が回転。
チェーンソー大剣の一振りが、ギルガメッシュの構えへと衝突。
完全に不意を突かれたのだ。
剣の重量。自身の加速度。刀身を覆う虹色の魔力。
いかに最強の英霊といえど、細身の剣の一振りで、三位一体の猛撃を受け止められるはずがない。
黄金の鎧は防御ごと弾かれ、ソファーから勢いよく投げ出される。
英雄王は玉座より落ち、無様に床を転げまわる。
「貴様……」
立ち上がるギルガメッシュ。灼熱の眼光が聖王を睨む。
こんな無礼者は初めてだ。
あろうことかこの男は、この英雄王の財宝を奪い取り、それを自分へ投げつけてきたのだ。
「言われた通り、落としたぞ」
怒りの矛先に立つ聖王は、無表情に自分を見下ろす。
許せない。
こんな屈辱が許せるものか。
こいつはこの場で八つ裂きにしてやる。この英雄王、直々にだ。
「約束だ。俺の母さんのこと、話してくれ」
巨大なチェーンソー大剣を片手で掴み、軽々と切っ先をギルガメッシュへと向ける。
「……そうだったな」
にやり。
されど、最強の王者は不敵に笑む。
この先にこの無礼者が浮かべる表情を想像すると、笑いが浮かぶのを止められなかった。
「いいだろう。教えてやる」
一拍の間を置き。
告げた真実は。
「『そんな奴は知らない』。それが我の知りうる情報だ」
「なっ……!?」
絶句。
赤と緑のオッドアイが、驚愕も露わに見開かれた。
そう。この戦いを始めた時から、彼女はこの時を待っていた。
乳離れもできない青二才が、母の情報への期待に胸躍らせるさまを、真っ向から粉々に打ち砕く。
「くくく……はっはっはっはっ……!」
何と爽快なことか。
何と痛快なことか。
呆けた表情を浮かべる聖王を前に、英雄王は大笑する。
最初からお前の望むものなどない。全てを支配していたのはこの我なのだ、と。
「ッ……なら、なのはだっ! 高町なのはのことを教えろ! あいつは……俺の母さんを奪ったあいつは、どこにいるッ!」
だが、まだまだだ。
当初ならこれだけで済ませる予定だった。
絶望に悲嘆するヴィヴィオの身体を、この剣の一撃で貫いて終わらせるつもりだった。
しかし、そうも言っていられなくなった。
「くく……そうだな。ならば次のゲームだ。これに勝てば、そいつのことを教えてやろう」
こいつは愚かな略奪者だ。
無礼にも王の宝具を奪い、その槍で刃向かってきたこそ泥なのだ。
ただ心臓を突き刺すだけでは生ぬるい。
こいつには真の絶望を教えてやる。
《王の財宝》、その無限の刃。
幾千幾万の雨を受け、五臓六腑の全てを粉微塵に引き裂かれながら、苦痛と恐怖の中で果てるがいい。
「――こいつに耐えられたならばなぁっ!」
刹那、至近距離からの乱撃が、ヴィヴィオ目掛けて襲い掛かった。
心を乱した聖王に、防御も回避もできるはずもなかった。
巨大なチェーンソー大剣を片手で掴み、軽々と切っ先をギルガメッシュへと向ける。
「……そうだったな」
にやり。
されど、最強の王者は不敵に笑む。
この先にこの無礼者が浮かべる表情を想像すると、笑いが浮かぶのを止められなかった。
「いいだろう。教えてやる」
一拍の間を置き。
告げた真実は。
「『そんな奴は知らない』。それが我の知りうる情報だ」
「なっ……!?」
絶句。
赤と緑のオッドアイが、驚愕も露わに見開かれた。
そう。この戦いを始めた時から、彼女はこの時を待っていた。
乳離れもできない青二才が、母の情報への期待に胸躍らせるさまを、真っ向から粉々に打ち砕く。
「くくく……はっはっはっはっ……!」
何と爽快なことか。
何と痛快なことか。
呆けた表情を浮かべる聖王を前に、英雄王は大笑する。
最初からお前の望むものなどない。全てを支配していたのはこの我なのだ、と。
「ッ……なら、なのはだっ! 高町なのはのことを教えろ! あいつは……俺の母さんを奪ったあいつは、どこにいるッ!」
だが、まだまだだ。
当初ならこれだけで済ませる予定だった。
絶望に悲嘆するヴィヴィオの身体を、この剣の一撃で貫いて終わらせるつもりだった。
しかし、そうも言っていられなくなった。
「くく……そうだな。ならば次のゲームだ。これに勝てば、そいつのことを教えてやろう」
こいつは愚かな略奪者だ。
無礼にも王の宝具を奪い、その槍で刃向かってきたこそ泥なのだ。
ただ心臓を突き刺すだけでは生ぬるい。
こいつには真の絶望を教えてやる。
《王の財宝》、その無限の刃。
幾千幾万の雨を受け、五臓六腑の全てを粉微塵に引き裂かれながら、苦痛と恐怖の中で果てるがいい。
「――こいつに耐えられたならばなぁっ!」
刹那、至近距離からの乱撃が、ヴィヴィオ目掛けて襲い掛かった。
心を乱した聖王に、防御も回避もできるはずもなかった。
◆
「ふむ……死体はいずこかへと吹き飛んだか」
顎に右手を添えながら、少々無念そうに呟く。
ずたぼろになり打ち捨てられた亡骸を見届けたかったが、どうやらやり過ぎてしまったようだ。
背後の壁を突き破り、ホテルの外へと飛び出したヴィヴィオは、このホテル内には影も形も見当たらない。
「まぁいいだろう」
ないものは仕方がない。
見つかりそうなら、外に出た時にでも探せばいい。
ひとまず聖王に見切りをつけ、金の長髪を翻し、英雄王は歩を進める。
「そういえば……」
ふと。
その途中で、脳裏に浮かんだ顔があった。
自分と同じサーヴァント。麗しき剣姫にして、誇り高き騎士女王――セイバー。
奴はここにいるのだろうか。
自分と同じように、この殺し合いに呼び込まれているのだろうか。
だとしたら。
顎に右手を添えながら、少々無念そうに呟く。
ずたぼろになり打ち捨てられた亡骸を見届けたかったが、どうやらやり過ぎてしまったようだ。
背後の壁を突き破り、ホテルの外へと飛び出したヴィヴィオは、このホテル内には影も形も見当たらない。
「まぁいいだろう」
ないものは仕方がない。
見つかりそうなら、外に出た時にでも探せばいい。
ひとまず聖王に見切りをつけ、金の長髪を翻し、英雄王は歩を進める。
「そういえば……」
ふと。
その途中で、脳裏に浮かんだ顔があった。
自分と同じサーヴァント。麗しき剣姫にして、誇り高き騎士女王――セイバー。
奴はここにいるのだろうか。
自分と同じように、この殺し合いに呼び込まれているのだろうか。
だとしたら。
「今度こそ手に入れてやる」
にやり、と。
戦場のそれとはまた違う、独特な笑みを浮かべるギルガメッシュ。
「あれは我のものだ」
彼女は実に素晴らしい。
騎士として、姫として、女として。この英雄王が想定しうる最高の逸材だ。
故に、何としてもこの手に掴む。己の后として迎えてやる。
他の誰にも渡しはしない。何があろうと、決して渡してなるものか。
かくして、最強最古の英雄王は出陣する。
なるべく迅速に。なるべく大胆に。
己が力を遺憾なく発揮し、この殺し合いを台無しにするために。
ついでにセイバーを我が物とするために。
ギルガメッシュは、王の道を歩み始めた。
にやり、と。
戦場のそれとはまた違う、独特な笑みを浮かべるギルガメッシュ。
「あれは我のものだ」
彼女は実に素晴らしい。
騎士として、姫として、女として。この英雄王が想定しうる最高の逸材だ。
故に、何としてもこの手に掴む。己の后として迎えてやる。
他の誰にも渡しはしない。何があろうと、決して渡してなるものか。
かくして、最強最古の英雄王は出陣する。
なるべく迅速に。なるべく大胆に。
己が力を遺憾なく発揮し、この殺し合いを台無しにするために。
ついでにセイバーを我が物とするために。
ギルガメッシュは、王の道を歩み始めた。
――ところで、この殺し合いにおいて、彼女が見落としていたことが1つある。
通常、参加者に与えられるランダム支給品は3つ。あまりに強力なものだった場合は、2つや1つだったりもする。
当然ギルガメッシュのランダム支給品も、《王の財宝》1つきりだ。
だが考えても見てほしい。
最強の英雄王の持つ宝具は、見ての通り想像を絶する破壊力を誇る。
それがその性能を最大限に発揮できる、所有者本人に渡ったのだ。
他の武器を削っただけでは足りない。あまりに都合のよすぎる配分。
通常、参加者に与えられるランダム支給品は3つ。あまりに強力なものだった場合は、2つや1つだったりもする。
当然ギルガメッシュのランダム支給品も、《王の財宝》1つきりだ。
だが考えても見てほしい。
最強の英雄王の持つ宝具は、見ての通り想像を絶する破壊力を誇る。
それがその性能を最大限に発揮できる、所有者本人に渡ったのだ。
他の武器を削っただけでは足りない。あまりに都合のよすぎる配分。
そう。
ここからが本題だ。
ここからが本題だ。
彼女が見落としていたものは、デイパックに納められていた説明書。
元の持ち主なのだから、そんなものは読む必要もないと、ゴミ箱に丸めて捨てられたものだ。
元の持ち主なのだから、そんなものは読む必要もないと、ゴミ箱に丸めて捨てられたものだ。
そこに書かれていた注意書きに、とうとうギルガメッシュは気付かなかった。
――この宝具を使用し戦闘すると、戦闘終了から6時間の間、使用することができなくなります。あしからず。
【一日目 深夜/E-4 ホテル跡内部】
【ギルガメッシュ@Fate/Stay night】
[状態]:健康
[装備]:《王の財宝》@Fate/Stay night(6時間使用不可)
[持物]:基本支給品一式
[方針/目的]
基本方針:この殺し合いを圧倒的な力で制圧し、ぶち壊しにする
1:殺し合いが終わった後は主催者を断罪する
2:余裕があればヴィヴィオの亡骸を見つけたい
3:乖離剣エア、《天の鎖》を手に入れたい
4:今後立ちはだかってくるであろう未知の強者達に期待
5:セイバーは我の嫁。性別? そんなものはささいなものだ。
※セイバーが女装した男であることに気付いていません。完全に女だと思い込んでいます。
※《王の財宝》の制限に気付いていません。
※ヴィヴィオが死んだと思っています。
※E-4のホテル跡のゴミ箱に、《王の財宝》の説明書が捨てられています。
[状態]:健康
[装備]:《王の財宝》@Fate/Stay night(6時間使用不可)
[持物]:基本支給品一式
[方針/目的]
基本方針:この殺し合いを圧倒的な力で制圧し、ぶち壊しにする
1:殺し合いが終わった後は主催者を断罪する
2:余裕があればヴィヴィオの亡骸を見つけたい
3:乖離剣エア、《天の鎖》を手に入れたい
4:今後立ちはだかってくるであろう未知の強者達に期待
5:セイバーは我の嫁。性別? そんなものはささいなものだ。
※セイバーが女装した男であることに気付いていません。完全に女だと思い込んでいます。
※《王の財宝》の制限に気付いていません。
※ヴィヴィオが死んだと思っています。
※E-4のホテル跡のゴミ箱に、《王の財宝》の説明書が捨てられています。
《王の財宝》。
その無限の軍勢の集中攻撃。
当然これをまともに受けて、彼が生き残れる道理はない。
いかに聖王ヴィヴィオと言えど、生きていられるはずがない。
そう。
事実として、彼は死んだのだ。
その死体は刃の激流に飲み込まれ、ミンチのごとくずたずたにされ、ホテルの外へと叩き落されたのだ。
ただし――一度だけ。
「……くっ……」
夜空の下、身をよじる少年が1人。
ヴィヴィオだ。
漆黒の装束も黄金の頭髪も、赤と緑のオッドアイも。
全てが傷一つつかぬまま、草原に横たわっていたのだ。
何故あれほどの攻撃を受けながら、彼がこうして生き残れたのか。
答えは簡単。彼が咄嗟にデイパックより取り出した、もう1つの支給品の恩恵だ。
――リヴァイバルカード。
使用した後、一度だけ復活することができるアイテム。
ヴィヴィオは確かに死んでいた。そしてそこから生き返った。これがこのトリックのからくり。
立ち上がり、歩みを進める。
ギルガメッシュに倒されたのは悔しいが、今は構っている暇はない。
ヴィヴィオにはより優先すべき目的がある。
どこにいるとも分からない、自分の母親を探すこと。
そして。
「……高町、なのは……ッ!」
自分の母親を奪ったあいつを、この手で八つ裂きにすること。
聖王の胸中を渦巻く静かな憎悪。
あいつだけは許さない。
あいつだけは必ず倒す。
あいつだけは俺の手で。
その無限の軍勢の集中攻撃。
当然これをまともに受けて、彼が生き残れる道理はない。
いかに聖王ヴィヴィオと言えど、生きていられるはずがない。
そう。
事実として、彼は死んだのだ。
その死体は刃の激流に飲み込まれ、ミンチのごとくずたずたにされ、ホテルの外へと叩き落されたのだ。
ただし――一度だけ。
「……くっ……」
夜空の下、身をよじる少年が1人。
ヴィヴィオだ。
漆黒の装束も黄金の頭髪も、赤と緑のオッドアイも。
全てが傷一つつかぬまま、草原に横たわっていたのだ。
何故あれほどの攻撃を受けながら、彼がこうして生き残れたのか。
答えは簡単。彼が咄嗟にデイパックより取り出した、もう1つの支給品の恩恵だ。
――リヴァイバルカード。
使用した後、一度だけ復活することができるアイテム。
ヴィヴィオは確かに死んでいた。そしてそこから生き返った。これがこのトリックのからくり。
立ち上がり、歩みを進める。
ギルガメッシュに倒されたのは悔しいが、今は構っている暇はない。
ヴィヴィオにはより優先すべき目的がある。
どこにいるとも分からない、自分の母親を探すこと。
そして。
「……高町、なのは……ッ!」
自分の母親を奪ったあいつを、この手で八つ裂きにすること。
聖王の胸中を渦巻く静かな憎悪。
あいつだけは許さない。
あいつだけは必ず倒す。
あいつだけは俺の手で。
「待っていて……母さん」
【一日目 深夜/E-4 ホテル跡西の草原】
【ヴィヴィオ@魔法少女リリカルなのはStrikerS】
[状態]:健康、高町なのはへの憎悪、聖王状態
[装備]:大剣・大百足@.hack//G.U.
[持物]:基本支給品一式、ランダム支給品0~1
[方針/目的]
基本方針:母親を探す
1:母親を奪ったなのはを殺す
2:ギルガメッシュは次に会ったら殺す
3:自分の邪魔をする奴は殺す
[状態]:健康、高町なのはへの憎悪、聖王状態
[装備]:大剣・大百足@.hack//G.U.
[持物]:基本支給品一式、ランダム支給品0~1
[方針/目的]
基本方針:母親を探す
1:母親を奪ったなのはを殺す
2:ギルガメッシュは次に会ったら殺す
3:自分の邪魔をする奴は殺す