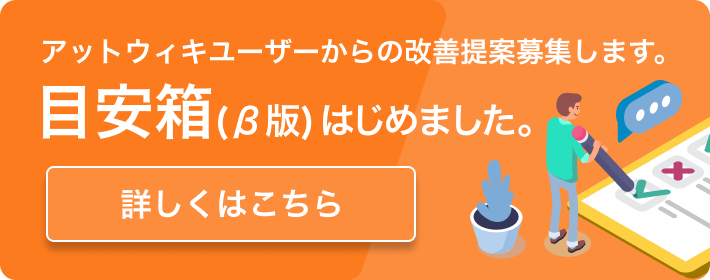銀腕軒のヌアザ
寒風も大分なりを潜めたとは言え、日が落ちれば冷え込むル・ガルの春の夜。
創作に行き詰まった相方、ではなく同居人、でもなく居候と言うのが妥当か?
ともかくもその居候に八つ当たりで追い出された身に夜気が冷たい。
(俺が家主のはずなんだがなあ……)
心の中で愚痴ってみるが、追いつめられた人間の迫力に尻尾を巻いた事実は変わらない。
当の居候の言葉を借りれば「状況末期の官僚とアニメ監督には逆らわぬが吉」と言うところか。
まああの移り気な居候の事だから小一時間も放置すれば落ち着くだろう。さしあたっての問題は
(ちょっと小腹が減ったかな)
胃の腑の寂しさを意識するとコートと毛皮越しにも寒さがしんと染みる。
(何かちょっと小腹に入れていくような店があったかな)
近所の地図を思い出しながら、夕食前のおやつを検討する。
喫茶店。近くの店はケーキしか置いてないから×。
定食屋。夕飯前に腹一杯になるから×。
パン屋。この寒いのに外でパン食いたくないから×。
パブ。飲んで帰ると何故か怒るだろうから×。
思い浮かぶ選択肢に×をつけてはのてくてと夜道を進む。
軽い空腹を抱えたまま、このまま帰っても構わないかな、などと思いつつ歩いていると
突然食べ物の匂いにぶつかった。
どこかで嗅いだような、だがよく思い出せない。上手そうな匂い。
興味をそそられて足を向ける。匂いにつられるままに二つ角を曲がると、その店はあった。
(屋台か……)
カウンターに三人座ればギュウギュウ詰めになりそうな小さな屋台。
赤い暖簾にはヒトの世界の文字で屋号であろう言葉が書かれていた。
『銀腕軒』
変わった屋号に眉をひそめつつ暖簾をくぐる。
「いらっしゃいませ」
「ああ……?」
出迎えたのは落ち着きに似合わない若い声。それを発した店主に目を見張る。
月の雫を集めたようなプラチナブロンド。
夕暮れ時の東の空の様な群青の瞳。
大理石を磨き上げたかのような艶やかな白い肌。
異国の神像を思わせるネコのマダラの美青年が、
「台無しだ」
「は?」
油染みたトレーナーと継ぎの入ったエプロンを身に纏い、捻り鉢巻きで髪をまとめていた。
「あ、いや。ちょっと居候に影響されたかもしれない。気にしないでくれ」
「はあ……」
暖簾をくぐれば、なんの匂いかすぐに思い当たった。ラーメンだ。
職場の安食堂のラーメンとは違う。スープからちゃんと作ったラーメンの匂い。
「一杯頼む。麺少なめで」
「はい、ただいま」
慣れた手つきで取り出した麺玉をほぐし量を調節する。その手元に何気なく目をやったとき、
動揺を隠しきれなかった。
腕まくりしたトレーナーから見える左腕がランプの明かりを受けて銀色に輝いていた。
アクセサリーでも鎧でもない、生物的なぬめった光沢の鱗に左腕が覆われていた。
驚いた気配に気が付いたのか、聞いてもいないのに苦笑しながら話し始めた。
「生まれつきでして。左腕と、あと尻尾も」
「キメラ……じゃないのか?」
「さあ?親が言うにはとんでもないウサギの呪いとか魔法とか」
「――っ!?親がいるのか?」
「父がネコで母がヘビなんです……と言ったら信じます?」
悪戯っぽい微笑みで返されて、その色っぽさに思わず惹かれそうになる。
男色の趣味があったのか、本気で自分を疑う。
「いや、まさか……」
なんとかそれだけ返して落ち着きを取り戻す。
落ち着きとともに脳裏に蘇る記憶。20年ほど前に流し見た報告書の回覧。
イナバ家に公的存在を抹消された魔法生命学の天才が沙漠に行ったらしいという伝聞情報。
(……それこそ、まさかだろう)
馬鹿げたネタを頭を振って追い出す。幻視でも出てこないような妄想の類だろう。
「お待たせいたしました」
差し出された丼がやくたいもない妄想を追い払ってくれた。
湯気とともに立ち上る醤油ダレとガラスープの混ざった食欲をそそる匂い。
具材はチャーシュー、ナルト、メンマ、海苔、葱。
シンプルでスタンダードと言えば聞こえはいいが、ありふれたなんの変哲もないラーメン。
(だが、うまい)
けれんみはいっさい無いが、故に不快さもない。ごちそうではなく、飯の味。
「いい腕だな」
「ありがとうございます」
「あいつも連れてくれば良かったかな」
「奥さんですか?」
「いや、そうなればな、とは思うが……。色々難しくてな。立場もあるし、気持ちもある」
「秘める恋ですか」
「いや、隠してもいないし伝わっているんだ。嫌われてはいないはずなんだがだからといって
好かれているとも……どうにも本音と冗談と妄言とデタラメの区別が付きづらくてなあ。
少し強引に動くべきかな、とも思うんだが……いやしかし……」
惚気とも愚痴とも独り言ともつかない呟きが勝手に口をついて出る。
しゃべりすぎだとは自覚しているが、聞かれて困る事を口にしなければどうと言う事もないし
その為の訓練は職業病のレベルで骨まで染みついている。
「……無言で押し倒すってのも、やっぱり必要かね?」
「どうでしょう。私、色恋沙汰にはとんと縁がないもので」
謙遜するな、と言おうとして止まる。
そっと、だが無視できない存在感で差し出された小皿。
ラーメンの上に乗っていた物とは違うチャーシュー。
「牛すね肉のチャーシューです。サービスですのでどうぞ」
「いいのか?まあありがたくもらうが……」
見た目は心までしっかりと火が入ってしまったローストビーフ。
だが、箸の先で触れて分かる。感触が違う。口に入れて確信する。
はらりとほどける肉繊維ととろけるゼラチン質。
ほどけた肉をかみしめるとじわりとしみ出す肉のうま味。脂肪の甘みではなく、アミノ酸の滋味。
臭みは必要最小限の香辛料で打ち消され、純粋に肉の旨さだけが舌に残る。
「良く煮えてるな」
「それは煮たんじゃないんですよ」
「え?チャーシューは煮るものだろう?」
「本来は焼くんです。獅子の字だと叉焼と書くんですが?
これは『フォークで刺して焼く』って意味の字なんです」
細い指先で空中に字を書き説明するマダラ。なるほど、言われてみればそんな字面ではある。
「けど、肉は焼くと固くなるだろう?」
「其処が誤解の元なんですが……肉の硬さは詰まるところスジの硬さなんですよ。で、スジってのは
ゼラチンみたいなもので出来てるんですね」
「ほう」
「で、ゼラチンみたいなものなので、水と一緒に長時間温めてやればだんだん溶けていくんです。
この時重要なのは、長時間温めるってところで温度の高さは関係ないんです。
煮たり茹でたりは水を媒介にしているから、肉に伝わる温度は100度以上にならないでしょう?
だから、焦がさずに長時間温めるって事が出来るわけです」
「あ、焼くとスジが溶ける前に焦げてしまうのか」
「ええ、だから焦げない程度の火力で、糖蜜をかけて肉の水分が逃げないようにした肉を
じっくり焙り続ければ、そのうちスジが溶けるというわけです」
「なるほどな」
そう納得しかけて、ふと疑問が湧いた。そのまま口に出してみる。
「じゃあこれは何時間ぐらいかけて焼いたんだ?」
「スープの仕込みと平行してやってますから……3~4時間って所ですか」
「4時間!」
たかがチャーシューに4時間。それを焦がさず焙り続けるのは店主のこだわり故か。
「確かにやたらと手間がかかりますが、それに見合ったものが出来ますし、
それに、作っている最中も結構楽しいものですよ」
「そんなものかな……」
「そうですよ。それに結果だけを求めるってのは、いかにも野暮じゃありませんか?」
チャーシューのアジトともに染みてくる言葉を味わう。
距離と拒絶、焦燥と独占欲、恐怖と不安、だがそれすらも気持ち一つで楽しめる。
そういいたいのか、このマダラは。
「色恋沙汰の話か?」
「旨い物を作るって話です」
はぐらかされて少し苛つきを覚え、すぐに気付く。直接口にするのも、やはり野暮か。
「うまかった。ご馳走様」
「あ、お客さんお釣り……」
紙幣を一枚置いて立ち去ろうとして、声がかけられた。
「チャーシュー代だ、とっといてくれ」
「いや、それでもこんなにはもらえませんよ」
「いーって、いーって」
「いや、そんなわけには……。そうだ、じゃあお釣りの分さっきのチャーシューを包みますよ」
「そうか?悪いね」
思ったより強情な店主の好意に甘える。手渡された油紙の包み。晩酌のつまみにいただくか。
「ありがとうございました」
「ああ、うまかったよ」
まだまだ冷えるル・ガルの春の夜。その夜道を少し早足で帰る。
少し重くなった右手と少し軽くなった肩に急かされて、少し早足で帰る。
書いてみた。校正なしで投下。
書いてみて分かった。……職人系ちょっといい話って、エロに繋げにくい!!
と言うわけで、これはシリーズ化無理ですな。