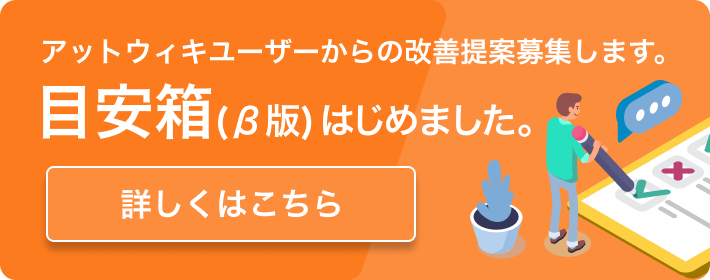ツキノワ 第1話
1.熊とあの世でティータイム
午前1時。
荒波の日本海を望む崖の上に一人、私は立っていた。
地面は靴の先から約3cmのところですっぱり切り落とされていて、切り立った岩に激しく当たっては砕け、泡立つ白い波頭をそこから見おろしている。
夏が去ったあと、ただでさえひと気のない漁村の海は朽ち果てたように見えた。聴こえるのは寂しげな波の音と、鳴き交わすかもめの声だけ。
水平線と夜の境目がわからないほどねっとりとした藍色の空間で、大きくカーブした湾のむこう、街の灯がひしめきあって瞬いている。そしてときどき雲の切れ間から覗く三日月の、冴え冴えとした白い光。
とはいえ私には、のんびりとこの景観を味わう余裕なんてなかった。ただひたすらに足元を凝視し、
(あはは。死ぬには今日が絶好の日和じゃない…)
負け惜しみにそんなことを考えながらも、恐怖で脚をガクガクと震わせていたので。
確かに自殺のロケーションとしては最高級だろう。二時間ドラマの帝王だってぐうの音も出やしない。
ただ残念なのは、風が完璧に凪いでいるということだった。これでは強風に煽られて体勢を崩し…という、内心期待していたアクシデントが起こる確率は少ない。
どうあっても、自分の意思で飛び込まなくてはならないということだ。
…海面まで30m以上はあるっていうのに。
こんな高さ、バンジージャンプだって恐ろしいのに、ヒモなしだなんてとんでもない。飛び降りたら間違いなく死んじゃいますよ、こんなの。
……いや、死にに来てるんですけどもね。
だってこんなに怖いのに、少しも『帰りたい』とは思わないし。
そもそも私にとっての帰る場所なんかもう、この世のどこにもないんだし。
(よし、…大丈夫)
自棄気味に大きく息を吸うと、潮と砂の混じった風が肺に満ちた。
小さいころ、まだ生きていた両親に連れられて来た海水浴の思い出が瞼のうらに蘇り、鼻の奥がツンとする。
懐かしく呼び覚まされたその記憶が、最後の一歩を後押ししてくれている気がした。
(いま行くよ…お父さん、お母さん)
親不孝して、ごめんね。
だけど親より後に死ぬんだし。ここまでひとりで頑張ってきたんだから、許してよね…。
でも実は内心、こうも思ってる。
小学校入学直後に親を交通事故でいっぺんに亡くしたときも、見たこともないような親戚たちがよってたかってウチのものを根こそぎ持ってったときも、それをただ歯軋りして見ていることしか出来なかったときでさえ欠片も思わなかったのに。
…たった一度の失恋くらいで自殺しようだなんて。
(ホント、馬鹿みたいなんだけどなあ)
実は、ここに来たのはただの思いつきだったのだ。
というより、崖の上でひとり火サスごっこでもすれば気分が出て、この重苦しい自己憐憫を少しは満足させられるだろう、なんて思っただけだったりする。
そもそもジェットコースターでさえ乗れない私にヒモなしバンジーなんて出来るわけがない。
どうせ恐くなってさっさと引き返すのは想像できたし、つまり本気なんかじゃ全然なかったわけで。
けれどねっとりと藍色に渦を巻く海を見下ろしていると、案の定凄まじい恐怖を感じながらも、その中に抗いがたい誘惑を感じてしまうのだ。
今! すぐに! 飛びこまなければ間に合わない! というような、妙に切迫した緊張感さえ――
「…え」
その時、ひゅうう、と風が吹いた。
完全に凪いでいたはずなのに、耳元を掠める笛のような生暖かい音色。
足元から吹き上げてきた突然のそれに、私は反射的に身を竦めた。
ただそれだけのことで。
私のヒョロい体はバランスを崩し。
「あ」
気付いたときにはもう、30mも下だったはずの渦が眼前に迫っていた。
アーイキャーン、フラーイ。
…あ、もう古いか。この台詞。
*
恐れていたような着水する瞬間の衝撃も、水中での呼吸困難もなかった。
運よく落下の途中で意識を手放したらしい。極度のビビリが良い方向に出た好例だ。
実に不幸で間抜けすぎる人生の終焉だったけど、このくらいせめてもの幸運だと思うことにしよう。
「………い」
あ、しまった。結局こうなるんならついでに遺書も書いとけばよかったよ。
…あんなくっだらないことが私の自殺の原因だなんて思って欲しくなかったけど、まあ、何を書いたところで『あいつ』はそう解釈するだろうしなあ。
別にそうしたければすればいいや。
ヘンに調子に乗るかむちゃくちゃ慌てるかするだろうけど、ま、死んだあとのことなんてどうでもいい。
「……っと、…しもーし」
でも、死んだあとでまで下世話な噂が広がっちゃうのはつらいなあ。
赤の他人のことを面白おかしく話すのは誰だって楽しいもんね。
…思えば、そういう人たちの無邪気な悪意にさんざん傷つけられてきた人生だったよなあ…。
せめて恨みのあるやつ全員、何発か殴ってせいせいしてからが良かった。ちっ。
そういや成仏せずにそいつら祟ってやるってのも手なんだよね。あんま気は進まないけど。
「…おーい。お嬢すわーん」
…何だよさっきから。この人なんなの?
あたしゃもう死んだんだよ。ほっといてくれよ。どうせ火サスごっこで本当に死ぬようなマヌケなんだから。
それとも何か、もしかして死に損なったのかな。どっかの岸に流れ着いたとか。ヤシの実か。
………いや! でも、ここってあの世だよね、絶対!
だって花の香りがするし、水の流れる音もするし、これって三途の川とお花畑ってやつでしょ?
海に落ちたってのに、こんなことありえないもん。
ということは何だろこの人…天国の番人みたいな人なのかな。
男の人の声だということはわかる。若い、とも言い切れないけど、そんなに年はとってないくらいの。
「参ったなこら。…お嬢さんよぉ、とりあえず起きてくんねっと話にならんのだわ、おおい」
大きな手でゆさゆさと揺さぶられ…た、のは、いいんだけど。
(……何でこの人、ちょっと訛ってんの?)
この状況で一番どうでもいいことがなぜか気になって、私はそおっと眼を開けた。
「お、ようやくお目覚めかね」
逆光で、すぐにはその人の顔が見えなかった。
ただ抜けるような青空の下に仰向けで寝かされている、という状況をぼんやりと察しただけだ。
「…あなた、は…?」
「そんなことよりおめぇさん、『ヒト』だな?」
こちらの質問をガン無視して当たり前のことを言われたけど、それでも私は頷いた。
なるほど、死んだものがすべてここにやって来るなら、三途の川を渡るのは人間だけではないのかもしれないと思ったのだ。
昔飼ってた犬のケンや、可愛がってたのに突然こなくなった野良猫のことが脳裏を過ぎった。
…もちろん、先立った両親のことも。
それにしても、なんかやけに体が重いのはどうしてだろう。手足にまるで力が入らないし。そして背中はひんやり冷たくて、ふわふわしてる。
海に落ちたはずなのに、体も服もまったく濡れてなかった。
霊魂ってのはこんな感覚なんだなあ、もっと身軽になるもんだと思ってた。なんてぼんやり考えていると、
「大丈夫か? …あぁ、とりあえず生きてて良かったわ。おめぇさんも運良かったな」
…なんだか意味のわからないことを言われた気がする。
それでもその時は頭の中に綿が詰まったみたいに、まともな思考が出来なかった。
「とりあえず運ぶな? …心臓に悪ぃかもしれんけど、あんまビックリすんなよ」
逞しい腕が背中に差し込まれたかと思うと、軽々と抱き上げられた。
その人の首に両腕を回し、肩に顎を乗っけられ、地面と垂直に戻された私の視界に飛び込んできた光景はというと。
…遠くからこちらへ順に色を重ねていくなら、まずは素晴らしく晴れ渡ったスカイブルー。
鬱蒼と生い茂る、果てが見えないくらい深い森のビリジアン。
陽光を浴びて乱反射する川のクリスタルは、空と木々の色を映してかすかに碧い。
そして足元に広がる色とりどりの花の絨毯。ピンク、イエロー、ブルー、パープル、その隙間から覗く茎と葉のライムグリーン。
私は花に詳しくないからよくわからないけど、スイートピーによく似てる。
人型にへこんでいる部分は私が寝ていた場所だろう。…かたじけない。
そして、何より問題だったのは。
「…あのぉ」
「何?」
「なんで、川から離れていくんですか…?」
三途の川を渡らないとあの世に行けないっていうじゃない?
それに私は死んだんだから、引きかえしちゃいけないんですよ?
愚かにも私は、その時本気でそう思っていた。
渡るもなにも向こう岸にはあのとおりの深い森があって、天国の扉なんてどこにも見当たらないんだけど。
「なんでってか? そらぁよ、おめぇさんをとりあえず落ち着かせんとな。ぜんぜんわかってねんだろこの状況」
「はあ…」
「手っ取り早く説明すっからよ、おめぇさん、ちょっと俺の顔見てみ」
――私には、まだ向こう岸に行く資格がないんだろうか?
そう思ったのはまるで見当違いだったけど、ある意味で正解でもあった気がする。
言われて素直に顔を横に向けた私は、とりあえず絶句した。
「…く?」
…やけに背の高い人だな。とは思ってたんだけど。
ずいぶんアタマでかいし、黒くて短い髪の毛はツンツンしててびっしり生えてるし。
肩ごしにちょっと見おろしたら、お尻にぽわぽわした大きい毛玉がついてるし。
息の掛かるほどすぐ近くにあるその顔はまさに、ご本人の言うところの、
「そうです。クマです。」
…いやいやいやいや。自己申告ですか。
まだここがあの世であると本気で思っていた私は、内心で突っ込むほど余裕があった。
あの世っていう特殊な世界だと思っていたからこそ「あれ? これ着ぐるみじゃね?」とも思わなかったし、ただなんとなく「あ、アッチの世界にはこーいう人もいんのかもネ」と納得したまでだったんだけど、彼にとってはそれが、かなり意外な反応だったらしい。
「へえ!? 驚かねぇの? …やぁ、見かけによらず剛の者だなあ、初めてだわこんなん」
「…はあ」
「だってよ、『落ちて』きたばっかの『ヒト』は大概、俺ん顔見ていきなり泡噴いて気絶すんのが普通だぜ」
「…はああ」
「はー、驚いた。いんや俺が驚いたわ。おめぇさんみてぇなの『心臓に毛が生えてる』ってんだろ、『ヒト』の世界では」
まあ、いうけど。私の心臓がどうなのかは別として。
熊男さんはどこか納得がいかないような顔(表情は読めないけど、なんとなくそんな感じ)ながらずんずんと川砂利の上を歩き、すぐ近くに建てられていた木造の小屋のなかに入った。
「ほい着いた」と言いながら私を椅子に座らせ、着ていた薄いコートのような服を脱いでハンガーにかける。
「ま、くつろいでくれや。いま茶ァ淹れっから」
「や、あの、おかまいなく…」
座らされたままの状態で固まっている私の前で、見かけによらず妙に几帳面らしい熊さんはテーブルの上にあった赤い保温ポットを取り上げ、粉を入れた木のマグカップにお湯を注いでいる。
明らかに異常な光景なんだけど、不思議なことにまったく違和感がなかった。
彼にとっては日常の行為なんだろうということがそれでわかる。
「これ便利だよなあ、『保温ポット』。こん中に入れとけば沸かした湯が全然冷めねぇんだもんな」
「…はあ」
「や、『ヒト』ってのはつくづくすげぇよ。…まあ飲んでくれや、『こーしー』」
「はあ。いただきます」
特に中身を警戒するでもなく、馬鹿正直にマグカップに口をつけた。
それは砂糖もク●ープもなしのネ●カフェで、あまりにも慣れ親しんだ味だったために、すっかり和んでしまった。
それどころか熊とあの世でコーヒーを飲んでいる、というファンタジーな状況が、なんとなく楽しくなってきてさえいたのだ。
「美味ぇか?」
「あ、はい」
「俺にはあんましわかんねっけど、おめぇさんらには美味ぇらしいな。こんな苦ぇのが」
「甘党の人は砂糖を入れるんですけどね」
「らしいな。…あ、悪ぃ、そうだった。おめぇさんも入れてぇか?」
「あ、いいえ。コーヒーはブラックでも平気ですから」
「遠慮せんでいいかんな」
「いえいえホントに。すいません気を遣っていただいて」
「そか。やー、どーも気ィきかんのよオッサン。だからかね、昔っからモテねぇの全然」
「あはは、そうなんですかぁ」
しばし向かい合って熱いコーヒーを啜り、マグカップのふちから覗かせた目でクマの頭を観察する。
小さめの目、黒い鼻、丸っこいふわふわの耳。
口吻も熊そのものなのに、うまいことカップの角度を調節して零さないように飲んでいる。
手の甲は熊の毛でずんぐりしてるけど、節くれだった五本の指は長くて、人間みたい。カップを持つのにも苦労はないようだ。
さっき上着を脱いでしまったので、頭から胸まで密集した真っ黒い艶やかな毛も全部見える。
「あ。月の輪熊さんなんですねぇ」
「ん? おお、そう」
上弦の月のような形の、白い毛の群。
…なんとなく海に落ちる寸前に見た、あの三日月を思い出した。
「『そっち』でもそう言うんだってな、俺みたいなの。『ツキノワ』って」
「そっち、というと?」
「『ヒト』の世界だよ。…おめぇさんはそこからこっちに『落ちて』きたんだ」
――落ちてきた? 私が?
「…『昇った』じゃなくて、ですか」
「こっちではそう言うな。おめぇさんらは空から落ちてくるもんだからよ」
「落ちた、っていうなら…ここってまさか『地獄』ですか!?」
今思うとものすごい見当違いなことを言ったと思うんだけど、熊さんは笑わなかった。
「違う。…と言いてぇけど、その『ヒト』によってはそう感じるかもしんねぇな」
「…どういう意味ですか?」
「ここじゃ、おめぇさんら『ヒト』は俺らの『奴隷』、よくて『ペット』の扱いだからだよ」
…恐らく意図的に声を低めて言われても、あんまりピンとこなかった。
何となくここが『あの世』でも『天国』でもなくて、ましてや夢を見てるわけでもなく、実は私は死んでなんかいなくて、というのは五感がしっかり働いてることで理解できつつあるんだけど。
じゃあどこなのよ、と考えれば――平たく言うと『異世界』っていうことになるのかな、とは思っていた。
RPGやファンタジー小説が大好きで、魔法使いに憧れたこともある私としては心躍る話だけど、とりあえずここはしっかりと熊さんの講釈に耳を傾ける必要があるだろう。
だってなにやら『奴隷』だの『ペット』だの不穏な空気がプンプンするし、RPGだって旅立ちの前には街の人の話をよーく聞くことが必要、というのがセオリーだし。
「あー…なんか悪ぃな。しょっぱなから強烈なこと言っちゃってよ」
熊男さんはなんだか申し訳なさそうにそう言った。
自分で「俺は気がきかない」と言っていたところを見ると、あまり口がうまい方ではないというふうに自覚しているんだろう。
でも、私はちょっと首をかしげた。確かに『奴隷』なんて言われれば腰も引けるけど、それがこの世界のルールなら、この人がそんなに恐縮することもないような気がしたからだ。
それにこの人の話し方はひたすら人の好い者のそれであって、不満を感じる人なんかいないと思うし。
「あ、でもな、俺らクマ族は他の種族に比べりゃすげぇヒトを優遇してるんだぜ。
首輪の着用と登録は絶対必須ってのはどの国も変わんねぇけど、奴隷! って扱いはしてねぇし。
そういう点ではそれほど悲観することもない、と、思うんだけどもさ…」
ふむふむ。私は大人しく相槌をうつ。
…他の種族、ということは、この世界には熊人間以外にもまだ半獣人がいるってことなんだろう。そしてこの世界の霊長はヒトではなく、その半獣人たちなのだ。
すごいなあ、まさにファンタジーだなあ、などと思いながら、今度はこちらから質問してみた。
「えっと。…ここでは私、首輪をつけなきゃいけないんですか?」
「え? ああ、違う世界の生物だからかもしれんけど、ヒトはこっちじゃすげぇ弱ぇし、すぐ死ぬモノっていう見方をされてんだよな。病気になりやすいし、俺らが冗談でちょっと叩いても大怪我するし…。
そのくせ市場ではおっそろしく高ぇ金額で取引される貴重品だから、他国じゃ盗難にも遭うらしい。
だから俺らん中の誰かが責任持って保護してやらんことにゃ、ヒトはここで平和に生きてけねぇのよ。
聞くところによると、だいたいおめぇさんらの世界の『ペット』と同じような立場ってことでさ、どこの誰のモンかっていうのを登録して、明確にしとく必要があるのさ。一応な」
そこまで一気にしゃべると、熊男さんはまたひとくちコーヒーを啜った。
なるほど、納得した。こっちでは飼い犬や飼い猫ならぬ、飼いヒトって立場なわけね。
まあ、どういう立場であるにしろ、こちらでは異邦人なわけだから、対等に扱われるってことはないんだろう。
…そういうもんだよなあ、どこの世界でも、とぼんやり思う。たぶん私たちの世界に宇宙人がやってきても、同じような扱いをするだろうし。
――それに同じ国に住んでて、同じ人間で、同じ血が流れていても、そういう扱いを受けることもあるんだし。
「えっと…私の他にも結構いるんですか? ヒトって」
「うん。村に帰りゃいっぱいいるし、あっちの世界の話もわんさと聞ける。俺たちはヒトの話が好きだからな。
おめぇさんも同じ境遇の仲間がいっぱいいるから淋しくないと思うぜ。……っていうかよぉ」
熊男さんは大きな顔をぐいっと突き出し、まじまじと私の顔を見た。
「…ほんっとおめぇさん、ビビんねぇよなあ」
「はあ…」
「さっきも言ったけどよ、大概落っこちてきたばっかのヒトはすっげぇ取り乱すぜ。
ここはどこだ、お前は誰だ、俺をもとの世界に帰してくれ、ってよ。
俺にはそういうヒトの気持ちはよくわかるけど…おめぇさんのその落ち着きは正直、わかんねぇわ」
「あははははは、なんでですかねぇ…」
とりあえず笑っておいたけど、確かにそうだろうと思う。
いわゆる『異世界』なんて想像上のものだし、実在するなんて誰も思ってない。なのにいきなりこんなところに落っことされて、平静でいられる人なんていないはずだ。
でも私は正直、あまりショックでもないし、悲観したりもしていない。
――というより、出来ない、というほうが正しいのかもしれなかった。
「…年に一度くらいの割合かね。この川にはおめぇさんみてぇに『ヒト』が落ちてくる。
俺の役目はこの小屋に常駐して、おめぇさんらを保護して、状況を説明することだ。こういうふうにな。
…何年やってもあんま巧く出来た試しがねぇんだけど」
「あ、だから、なんか詳しかったんですね」
「ん?」
「そのポットとかコーヒーとかすごく馴染んでましたし、私の世界についての知識も」
「うん、こういうのは全部おめぇさんらの世界から落っこちてきたモノだ。
…つっても俺らにゃ使い方なんか全然わかんねっから、ヒトに教えてもらって初めてわかるっていう有様なんだけどもね」
これ見てみ、と保温ポットを持ち上げて側面を見せてきた。
なるほど。高いところから落ちてきたものらしい、無残なへこみが残っている。
「うわ…私も空から落ちてきたんですかね?」
「今まで落ちてきたヒトを見る限りそうだと思うぜ。…まったく憶えてねぇのか、落ちた瞬間のこととか」
「ないんですよねえ、それが…」
「見たところ怪我もねぇよなあ。…なんなんだおめぇさん」
「あはは…」
「半数以上は落下のショックで死んじまうんだぜ。俺、今まで何人も墓つくって埋めたもん。
あとは落愕病つってな。あっちでの記憶を無くしたり、言葉が話せなくなったりするヒトもいる。
おめぇさん、向こうの世界にいたころの記憶は確かか?」
「…生憎、それもはっきり憶えてんですよねえ…ははは…」
熊男さんは目を何度か瞬き、ゆっくりとコーヒーを飲んだあと、横をむいてひっそりと言った。
「…あんまし、いい思い出がねえのか」
「まあ、そういうことです」
「帰りたいとも思わない?」
「…うーん。帰る家がねぇ、ないんですよ、あっちでも」
――そう言った自分の言葉で、どうしてこの状況で冷静でいられるのかを理解した。
私はさっき目覚めた時点で『死んだ』気でいたし、ここを『あの世だから何が起こっても不思議じゃない』と思っていたのも、大きな理由だったんだけど。
「………奴隷ってほどでもないけど、人間扱いされてたって感じでもないし。
だから、私、どこにいたっておんなじなんですよね。きっと」
なんでこんなこと言っちゃったのかなあ、と、言った瞬間にもう後悔していた。
このいかにも人の好い熊さんに言ったところで、これから始まるだろう完全な『奴隷』生活には何ら光明もないだろうし、今までの経験上、手放しで同情されることにもすっかり飽きていた。
――そのはずだったのに。
この人は絶対こう言うだろうな、ということも予想していたのに。
「…なんでって、訊いてもいいのかね」
あなたには関係のない話ですよ、と言うことも出来たんだけど。
なんかこの際だから聞いてもらっちゃおうかなあ、と思ったのは何でなんだろう。
ぼんやりとそんな疑問を感じながら、だけど口は勝手にすらすらと動いていた。あるひとりの少女の辿った悲劇、という名の喜劇を語るために。
「つまんない、よくある話ですよ。
手始めに小さいころに両親を亡くしましてね。家のもの全部持ってかれて、親戚中たらいまわしにされて、どこ行っても『いないもの』みたいに扱われてきまして。
ついたあだ名はストレートに『みなしご』でしたし、だから性格暗かったし、ちょっとオタクだったし、教室ではひとりで絵ばっか描いてて友達もできなかったし、お金なくて行きたい学校にも行けなかったし。
だからとっとと自立したくて日夜せっせと働いてたんですけど、その熱意も虚しく会社がおととい倒産したんですよ。マジで。
おまけについさっきですよ、人生で初めて付き合った男の人にもこっぴどくフラれたんですよね。
なにもこんな時に! って思って、そんでもーヤケんなって自殺してやるとか思って崖っぷちに立ってみたりして、でも怖いからやっぱやめようかなーとか思ったところで風に吹かれて落ちたんです、ものの見事に。
ほんとに死ぬ気なんかなかったのに。
なんなんでしょうねこれ?」
私はいつもこういうとき、得意の噺を披露する落語家の気持ちになる。
だけどひと息に言ったらなんかおかしくなってきて、最後のほうではちょっと笑ってた。なんかもう絵に描いたみたいな薄幸人生で、自分でも嘘なんじゃないかと思ったのだ。
熊男さんは目をまるくして聞いててくれたけど、私が笑ってるのを見て、何か感じ入るところがあったらしい。
「はあ、そっか。でもそれ、もうおめぇさんの中じゃ過ぎたことなんだなあ」
「え?」
「なんか、こう…俺口下手だから巧く言えねぇし、ヒトの世界の事情とかよくわかんねっけど、すげぇ大変だったんだろうなって思うよ、ここまで生きてくの。
でもおめぇさん、それを冗談っぽく言ってるけどさ、ほんとはあんまし『自分は不幸だ』って思ってねんじゃないのかって、俺は感じた」
思わず声をなくした私に、熊男さんはたぶん、笑ってくれた。
表情はわからないけど、そんな感じの息をついて、こう言ったのだ。
「頑張り屋さんだ。強ぇな、おめぇさんは」
――そんなことを言われたら。
すっかりつめたくなったマグカップを、両手で強く握った。何かにつかまっていないと流されてしまうと思ったから。
もうこれ以上なにも話すことなんてないと思うのに、やっぱり口は勝手に動く。
「…私が…自分の人生をおもしろおかしく語ると、みんな喜ぶんですよねぇ」
「うん」
「まあ確かに運もなかったですし、血縁関係も悪かったし、ネクラだから人にも避けられてましたけど。…私にとってはこれが、普通だったんですよ」
「そうだろなぁ」
「自分が不幸だなんて思いたくなかったですよ。だけどそうやって笑い話にしないとやってけなくて。不幸だ不幸だってアピールしてないと、なんかこう…参加できないような気がしたんです。世の中に」
何が正しい考え方で、どういうふうなやり方がよかったのか。
もう帰れないだろうあの世界に思いを馳せても、今でもまったくわからない。これしかやり方を知らなかったし、今もやっぱりわからないのだ。
それでも、これから新しい世界での生活が始まるんだろうな、とぼんやり思う。
私は希望を持つ、ということが巧くないし、のっけから『奴隷』なんていう素晴らしい境遇からのスタートだけども。
「私は…この世界で、どう変わってくんでしょうかねえ…ふふふ」
「おいおい、他人事みてぇな言い方すんなよ。しかもなにその不気味な笑い」
「や、もうどーでもいーなーって気持ちと、ちょっとワクワクしてるのと、半々なんですよね」
「…醒めてんなー。もっと情熱を持てよ情熱を。おめぇさん、せっかく可愛いのに」
最後の一言は聞かなかったことにしよう。
そう思ったのにも関わらず、未熟な私の顔の毛細血管は過剰に反応していたらしい。
「お。顔赤ぇ!」
彼は興味深そうに熊顔を突き出してくる。
私は椅子の背もたれに思いっきり体重をかけてのけぞり、顔を背けた。
「か、からかわないでくださいよ…そんなこと彼氏にだって言われたことないんですから…」
「はあ? なんだそいつ。さっきの話に出てきたやつか?」
「だ、だから言ったじゃないですか。初めての彼氏だったって」
「…そんなやつのどこが良かったのよ?」
思わず口ごもった。
我ながらくだらない理由だと思ってはいたんだけど、…どういうわけかそれよりも、この熊さんに対して後ろめたい気がしたからだ。
…いやいや何をおっしゃる。確かにこの熊さんはイイヒトだけども、なにもそんな。ねえ。
だって熊だし。…熊だよ?
いやいやいやいや。あれだよ。せっかく親身になって話聞いてくれたってのに、こんなくだらないこと聞かせてゲンメツされるのもヤだしね。そんだけだよね。
つか、「口が巧くない」とか言っといてなんなんだこの人。言葉の選び方はどうか知らないけど、さっき言ってくれたアレは、私にしてみたら超ド級の感動モノだったんですけど。
「頑張り屋」も「強い」も今まで何度も言われたし、通信簿に書かれてきたのも大抵そのふたつだけど、これほど嬉しい言われ方はしたことないんですけど。
なんなんだよ。…すごいイイヒトじゃん、この熊さん。雰囲気でわかっちゃいたけどもさあ。
「えっとぉ…その…」
「何さ」
「うん…まあ、ええと。…つまり、腹筋が、ですね…」
「はあ?」
「…会社の同僚で、陸上部出身の人でしてね。それはそれはキレーに、8つに割れててですねえ……」
「………腹筋がか」
「え、えへ…」
…本当にくだらないな、と今では思う(感覚ではつい数時間前のことなんだけど)。
私は昔から腹筋に限らず、筋骨逞しい男が好きだった。ちょうどミケランジェロのダビデ像みたいなやつ。あれがすごい好きで、美術の教材とか何時間も見てハアハアしてたりしてましたよ。…恥ずかしながら。
芸能人は顔とか演技とかじゃなくて、ガタイでファンになってたし。ム●フシとか。あれは芸能人じゃないけど。
要するにフェチっていうか単純に好みなんですよね、巨乳好きの男の人とおんなじような感覚で、ええ。
今考えてみると中身とかどーでもよかったんですよね。うん。
だってあいつやたら筋肉自慢してたし、飲み会とかで酔っ払ったフリして脱いで、人に見せつけるの大好きだったしなあ。
…うわ、ナルじゃん。完璧。
なんでもっと早く気付かなかったんだろ…そりゃあんなことされたって文句言えないよなあ。
「なんだ。おめぇさんの好みの男ってのはつまり、腹筋が割れてりゃいいのか」
「いやその、もう違いますよ!? 懲りましたよさすがに。やっぱ男は中身ですよ、中身!」
「ふん。腹筋なら俺も割れてんだかんな」
「あ、ほんと…ですね…」
「ちょっおま、何じろじろ見てんの! もう懲りたんじゃねーのか!」
「ああああはいはいはいはい懲りました、もちろん懲りましたとも!」
ていうかこの熊さんも何を張り合ってんだ、あんなくだらない男と。
…って、すいません。一番くだらないのは私でした。猛省。
………あ…でも熊男さんの腹筋のほうがヤツなんかより数倍すご…いやいやいやいやいや!
「で、あの! …私はこれからどうなるんでしょうね!」
「うん、えっと、そだな、まずは村に行かないことには話になんねんだけども…」
「…うはぁ…競にでもかけられるとか…?」
「いやいやそんなことしねぇよ。それに今は村に行ったって誰もいねぇしな」
「なんでですか?」
「なんでって、冬眠してんだよ、皆」
「とうみん!?」
「たりめーだろ。俺らクマだぜ?」
いやそらそうかもしれませんけども。
そういう習性なんなら私が口を出すことでもないんだけど、ちょっとそりゃおかしいんじゃないのか、という気がしなくもない。
何と言っていいのかわからずに眉間にしわを寄せていると、熊男さんはその空気を察したらしい。
「や、おめぇさんの言いたいこともわかんだけどさ。しょーがねーのよクマだから」
「はあ…」
「まあ俺らの国は一部の種族を除いて国交断絶してるようなもんだし、他国の干渉もねぇから、あんま不便ではないわな。
なんたってみんなで寝ちまえば一緒だし、『結界』があるから、外からは誰も入ってこられんのよ。
まあ、そこの花が咲き始めたから、あと数日でみんな目覚めるはずだわ。そんなにかからん」
…なんか今、ちょっと興味深い単語が紛れてたような気がするぞ。
よし、無知を装ってさりげなく訊いてみよう。
「…えっと…結界っていうのは…?」
「クマの国はな、…まあ話せば長くなるから今は割愛すっけど、大陸にあって大陸にないんだな。
特殊な結界を張って、存在を切り離してる。ま、いわゆる『半異次元』に存在してる状態になってるわけさ」
…なんだかややこしい話になってきた。
RPGの世界観を理解するのは簡単なんだけど、いざ自分がその只中に置かれると、どうもピンとこないのはなんでだ。
「…はあ…なんか、私の世界でいう鎖国みたいなもんですか」
「ああ、なんかそんな話をいつかヒトがしてたな。似てはいるけど、もちっと徹底してると思うぜ。
地図上に俺らクマの国は確かにある。でも実際そこに足を踏み入れたとしても濃い霧が立ち込めてるばかりで、街も人もどこにもない」
「幻みたいな感じですか」
「まあ、そうだな」
「内から出て行くことは出来るんですか?」
「もちろん。俺らクマの誰ひとり、その結界を潜れない者はない。結界はクマのためのものだから。
だけどクマじゃない者は誰ひとり、許可なく出入りはまかりならん。…とまあ、こういうことなわけ」
「ヒトも、ですか」
「もちろんヒトもだ。クマに飼われてるヒトなら別だけどな、主人と一緒ならいいんだ」
「他の種族の人たちは?」
「あらかじめ許可をとる必要がある。昔は本当にどことも国交を断ってて、国内にはクマとヒトしかいなかったんだけどな。
最近ではシカだのヤギだの、一部の国の一部の商人とは交易したりしてる。ほんとに一部だけどな」
「それは誰が許可するんですか?」
「俺」
やけにきっぱり言い切った熊男さんを、思わず凝視した。
目をまるくしている私のために、彼はもう一杯コーヒーを淹れてくれる。
「ま、おめぇさんには悪いけど、完全に春が来るまではここにいてもらうことになる。
…だからそれまで、ゆっくり話してやるよ。この国のこと、この世界のこと、いろいろな」
「それは…はあ、是非お願いしたいんですけど…」
「うん?」
…なんだろ、これ。
頭に浮かんだたった一言。これを口に出すのが、すごく、躊躇われる。
ていうかなんだろこの動悸。
いやいやいやいや、ありえないってマジで。
だってこの人…熊だよ。熊なんだよ!?
確かに腹筋すごいけど、だからって熊なんですけど!?
しかも数日とはいえ、この人と2人っきりでいなきゃなんないとか何の拷問ですか?
べ、別に嫌なわけじゃないんだからねっ!? …ってツンデレの言うことじゃねえー!
「その…名前、を。まだ聞いてなかったなって、思って」
「ああ、そういやそうだった。悪かったな、俺はウルだ。おめぇさんは?」
「三池安子、です」
「ミイケ・ヤスコ? てことは…お前の名前はヤスコか。後ろのほうのやつが名前なんだもんな」
「はい。でもその名前、あんまり好きじゃないんで…なんか新しい名前、ないですかね?」
「新しい名前って、おめぇさん、俺が名付け親でいいのか」
「はい。ダメですか?」
「ダメってこたねぇけど、俺センスねぇかんなぁ。……うーん。ミイケ、…ミーケ…ミケ…」
ウルさんは真面目に考え込んでいる。
…私のために一生懸命になってくれてる男の人って、なんか…いいなあ。
これから先に待ち構えている困難になんかちっとも考えが及ばない私は、ニヤニヤしながらウルさんの三日月模様を眺めていた。
ましてや――この夜、私たちがどうなってしまうかなんてことも。
【続】